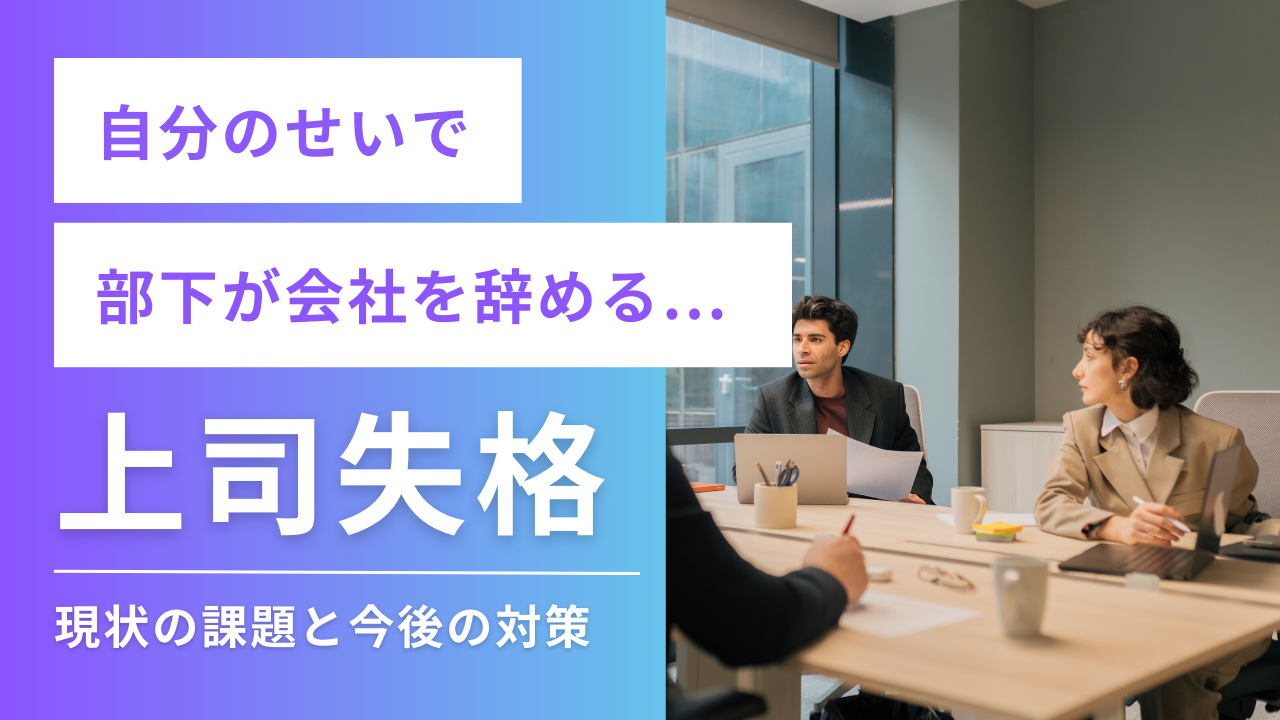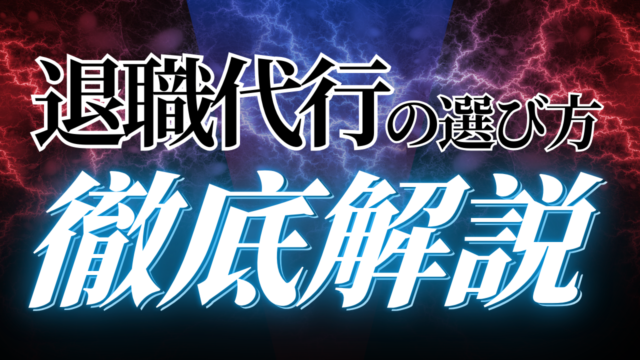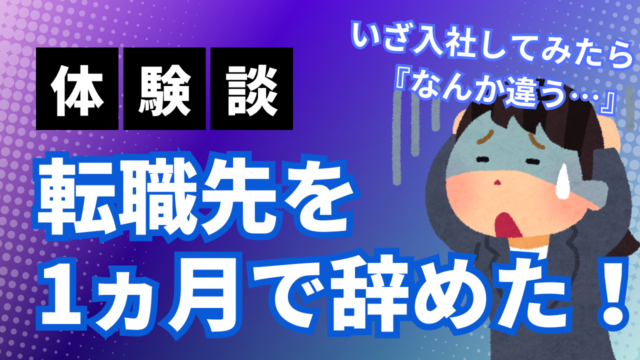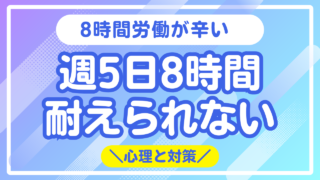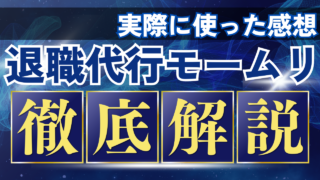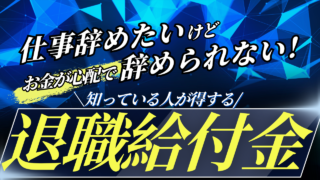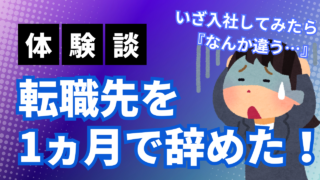「退職の理由は何?」と聞かれたとき、部下は本音を言わないことがほとんどです。
「家庭の事情」「キャリアアップのため」など、建前の理由を述べることが多いですが、実はその裏に上司との関係があることも。
さらに、退職理由が「ハラスメント」「コミュニケーション不足」など、上司の自分のせいで社員やパートが辞める場合は辛いですよね。
本記事では、社員やパートが辞める上司の特徴を解説し、次の新人が辞めないようにする対策について解説します。
- 部下の退職理由が自分のせいだった人
- 人が辞めていく現状をどうにかしたい人
部下の退職理由は本当に「自分のせい」なのか?

部下が退職する理由はさまざまですが、上司の影響が大きいケースも少なくありません。
「自分のせいで辞めたのかも..」と感じたことがあるなら、一度その原因を見直してみましょう。
退職理由の建前と本音
部下が退職するとき、「家庭の事情」「キャリアアップのため」などの理由を挙げることが多いですが、本音は違う場合があります。
部下はスムーズに退職するために「ウソ」を付くのです。
上司が部下の本当の気持ちを理解できていないと、同じ理由で退職者が続く可能性があります。
会社や仕事内容ではなく「人間関係」が原因のことも
待遇や業務内容に問題がなくても、上司との関係が悪化すれば退職を考える人は多いです。
「報連相がしづらい」「叱責ばかりで評価されない」「相談しても取り合ってくれない」などの状況が続けば、部下は「ここで働くのは無理だ」と判断します。
部下の退職理由が「自分のせい」だった場合
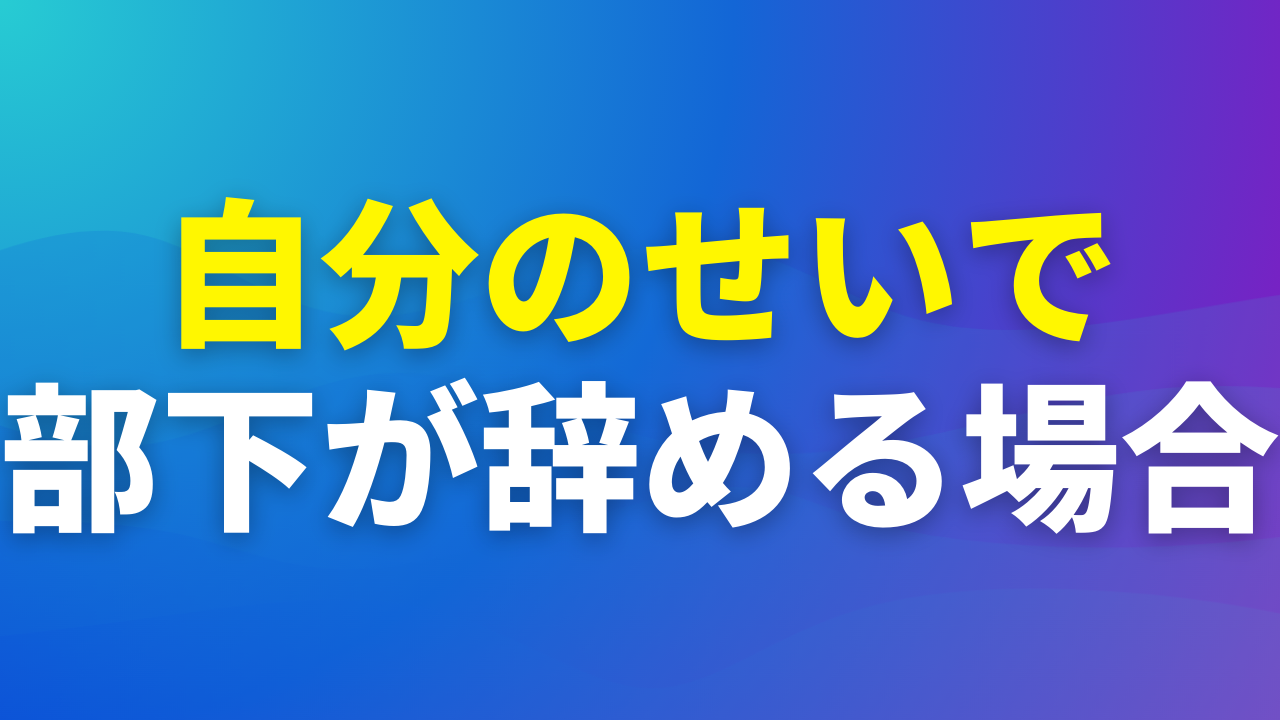
部下の退職理由が「上司のハラスメントがきつい」「上司からの評価が正当じゃない」など、自分のせいの場合、あなたの行動を改める必要があるかもしれません。
また、部下が上司のせいで会社を辞めると、上司の評価も落ちます。
この際に「あいつが辞めたから俺の評価が落とされた」と考えるのであれば、あなたは上司失格です。
まずは、何が原因で退職に至ったのかを理解しましょう。
何が原因で部下が辞めるキッカケになったのか
部下が辞める直接の原因は、上司の言動にあることも少なくありません。
過度な叱責、過剰な業務負担、評価の不公平さなどが積み重なると、部下の心が離れてしまいます。
そのような行動をしていないか、上司自身が「何がキッカケだったのか」を振り返ることが、今後の対策につながります。
自分のせいで部下が退職する人の特徴
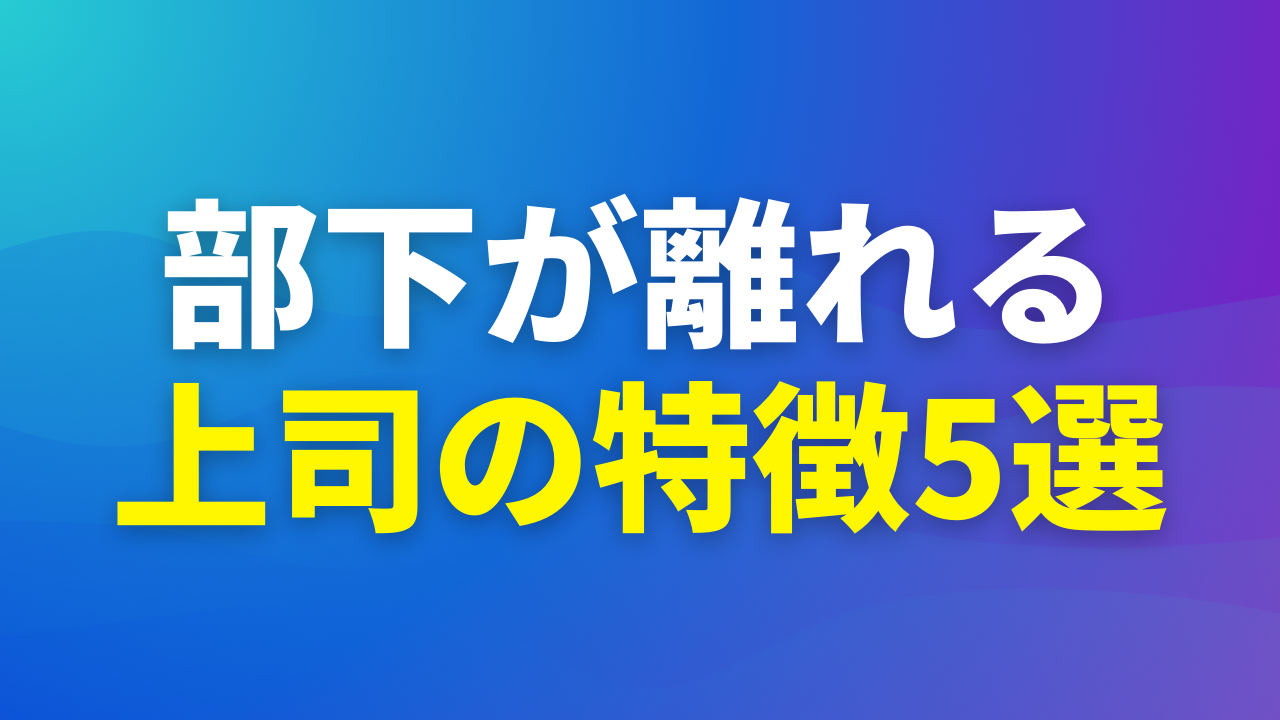
部下の離職が続くなら、上司自身の言動を見直すことが重要です。
どのような特徴が部下の退職を招くのか、確認してみましょう。
- 感情的に叱る、指導が一方的
- 部下の意見を聞かない
- 仕事を丸投げする or 細かすぎる
- 感謝や評価をしない
- 公平でない対応をする
感情的に叱る、指導が一方的
感情的に怒る上司は、部下にとって恐怖の存在になります。
また、一方的な指導ばかりでは、部下は成長の実感を持てず、不満が蓄積されていきます。
部下の意見を聞かない
「上司の言うことが絶対」という考えのもと、部下の意見を無視すると、部下は「ここでは何を言ってもムダだ」と感じてしまいます。
結果として、モチベーションが低下し、最終的に退職につながります。
仕事を丸投げする or 細かすぎる
部下に仕事を丸投げし、適切なサポートをしない上司は、部下に大きなストレスを与えます。
一方で、細かすぎる指示や過干渉も、部下の自主性を奪い、働きづらさを感じさせます。
感謝や評価をしない
どれだけ頑張っても「当たり前」とされる職場では、部下のモチベーションは低下します。
適切なタイミングで感謝の言葉や評価を伝えないと、部下は「自分は必要とされていない」と感じ、退職を考えるようになります。
公平でない対応をする
一部の部下だけを贔屓(ひいき)したり、不公平な評価をしたりする上司は、職場の不満を生みます。
「どうせ評価されない」と思った部下は、努力をやめ、最終的に辞める選択をすることも。
今すぐ辞めたほうが良いヤバイ上司の考え
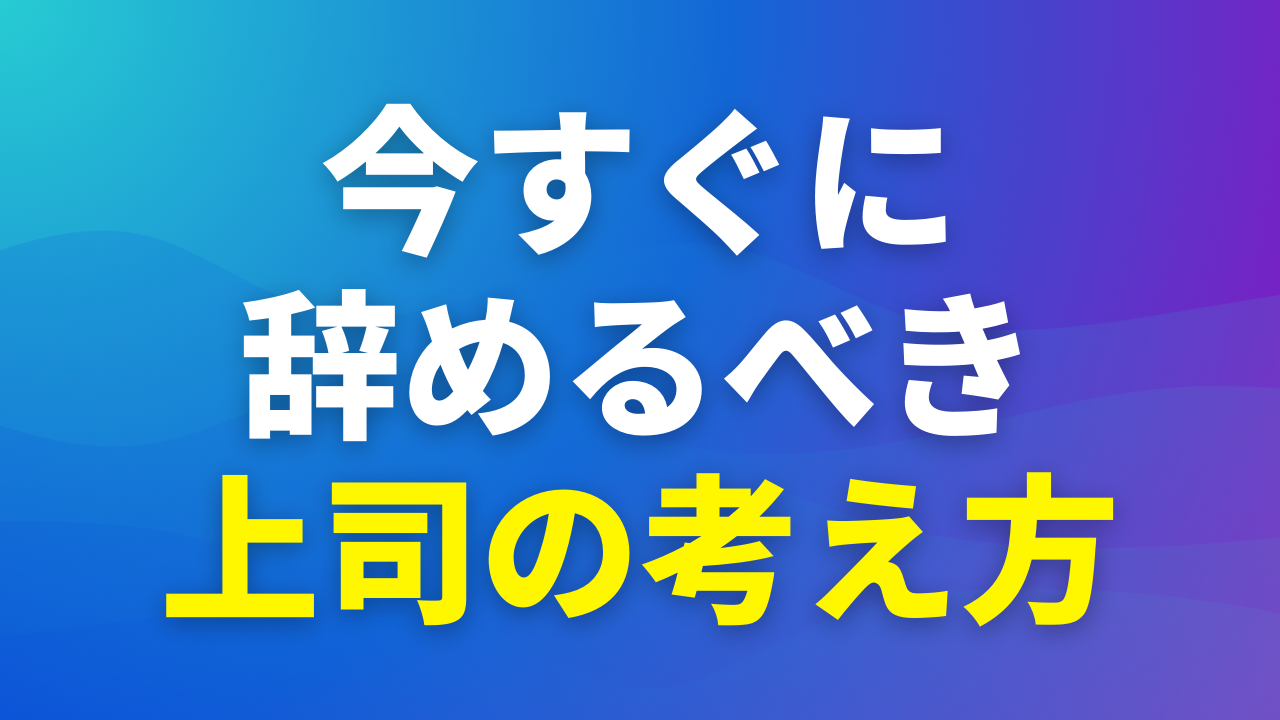
上司の考え方や価値観が古いままだと、部下の退職は止まりません。
下記のような考えを持っている場合は、すぐに改善が必要です。
- 今の新人は考えが甘いな
- 入れ替わりの激しい業界だから
- 部下が辞める理由が自分のせいと気づいていない
今の新人は考えが甘いな
「最近の若者は忍耐力がない」「自分の頃はもっと厳しかった」などと考える上司は、時代の変化についていけていません。
こうした考えでは、部下との信頼関係は築けず、離職が続く原因になります。
入れ替わりの激しい業界だから
「この業界は退職が多いのが普通」と考えていると、部下の離職の原因を見直す機会を失います。
根本的な問題を解決しない限り、常に人手不足に悩まされることになります。
部下が辞める理由が自分のせいと気づいていない
部下の退職を「本人の問題」と決めつける上司は、同じミスを繰り返します。
「自分の悪いところはないか」
「退職する社員に対して、どんな行動をしていたか」
のように、自分の関わり方を見直す必要があるかもしれません。
部下が辞めない上司になるために
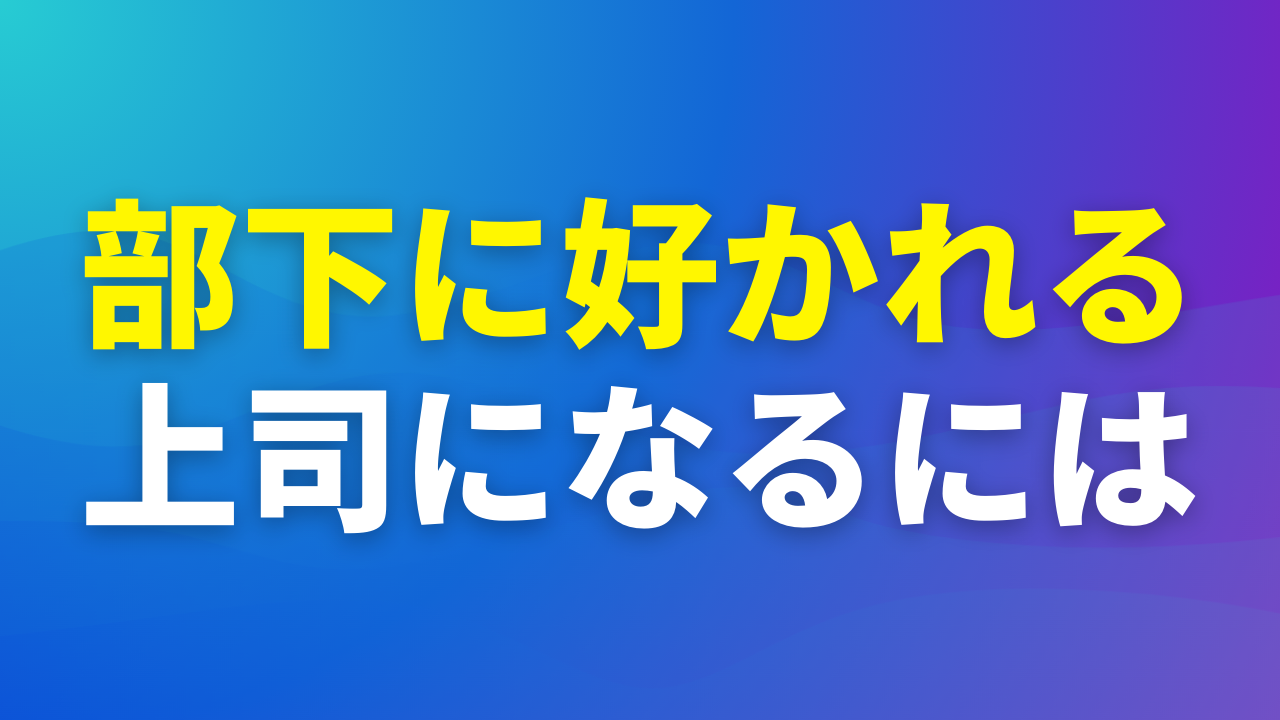
部下が定着する職場を作るには、上司の姿勢が重要です。
どのような行動が信頼関係を築くのか、具体的に見ていきましょう。
- コミュニケーションの見直し
- 部下のモチベーションを理解する
- 信頼関係を築く習慣をつける
コミュニケーションの見直し
定期的な1on1や、部下の話をしっかり聞く姿勢を持つことで、信頼関係を築くことができます。
上司から積極的に話しかけることも大切です。
部下のモチベーションを理解する
部下が何を求めて働いているのかを知ることで、適切なサポートができます。
昇進・スキルアップ・働きやすさなど、個々のモチベーションを把握しましょう。
部下も人間なので、価値観や性格は十人十色。
それぞれがモチベーションに感じる部分を探るのも上司の役割です。
信頼関係を築く習慣をつける
日頃から感謝を伝え、成果を評価することで、部下との信頼関係が深まります。
また、公平な対応を心がけることで、「この職場で働きたい」と思ってもらえる上司になれます。
まとめ
部下が辞める理由にはさまざまな要因がありますが、上司の対応が大きく影響しているケースは少なくありません。
感情的な指導、不公平な対応、コミュニケーション不足などが、部下の退職につながることも。
「自分のせいで部下が辞めたのかも」と思ったら、まずは自分の言動を見直し、部下との関係を改善することが重要です。
信頼関係を築き、部下が安心して働ける環境を作ることで、退職を防ぐことができるでしょう。

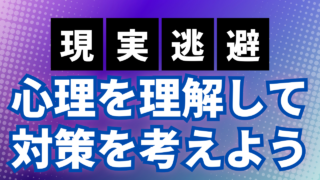
私の転職に対する考えが変わった1冊の本を置いておきます。
オリエンタルラジオ中田敦彦さんも絶賛した、LinkedIn日本トップの村上さんの「転職2.0」になります。
ぜひ興味がある方は読んでみてください。