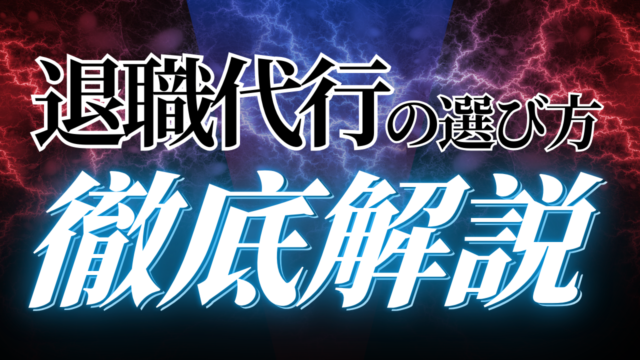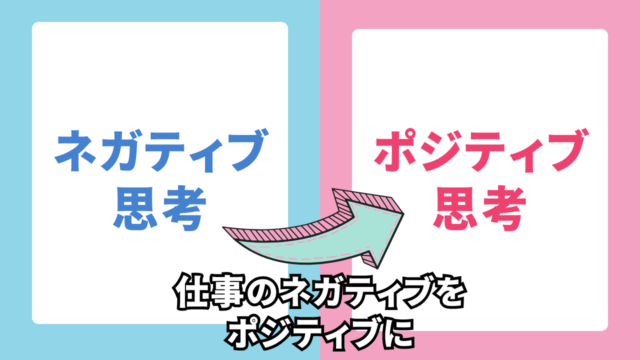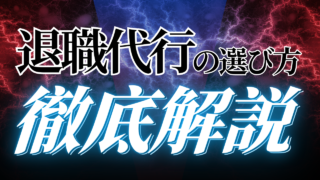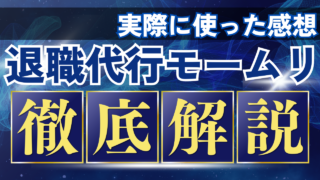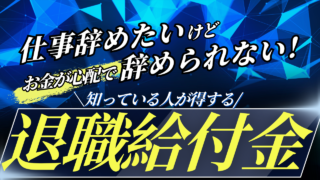「またフォローか..。正直、しんどいな。」
仕事ができない人のフォローに疲れていませんか?
ミスをカバーしたり、仕事を教えたり、気を遣ったり..。本来自分の仕事に集中したいのに、フォローばかりでストレスがたまる。
そんな毎日が続くと、「もう関わりたくない」とさえ思ってしまいますよね。
この記事では、仕事できない人のフォローで疲れる原因や対策、ダメな行動などを解説していきます。
- 仕事ができない人に疲弊している方
- 仕事ができない人を拒絶してしまっている方
仕事できない人のフォローで疲れる人の特徴5選
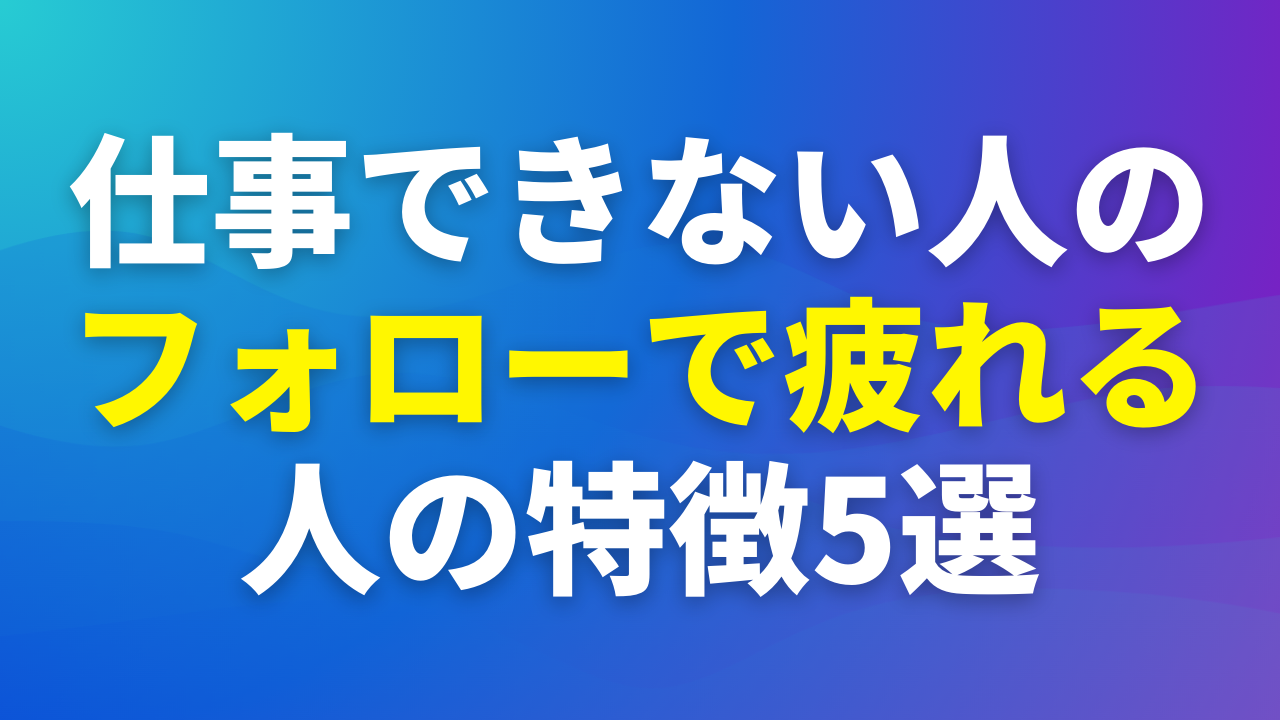
仕事できない人のフォローで疲れやすい人には、いくつかの共通する特徴があります。
真面目で責任感が強い人ほど、つい助けすぎてしまい、自分の負担がどんどん増えてしまうことも..。
ここでは、フォロー疲れしやすい人の特徴を見ていきましょう。
- 責任感が強い
- 真面目で手を抜けない
- 周りに気を遣いやすい
- 仕事の効率が良すぎる
- 自分のキャパを超えても頑張ってしまう
責任感が強い
責任感が強い方は、「自分がやらなければ」と思ってしまい、フォローをしてしまいます。
チームの成果やクライアントの成果を考えるあまり、仕事ができない人のミスや遅れもカバーしようとする傾向があります。
真面目で手を抜けない
「適当にやるのは嫌」「ちゃんとしたクオリティで仕上げたい」と考える人ほど、フォローで疲れやすいです。
手を抜けない性格がゆえに、他人のミスを見過ごせず、つい自分が修正したりしますよね。
周りに気を遣いやすい
「○○さん、困っているかな?」「このままではチームに迷惑が掛かる」と気を遣いすぎると、無意識にフォロー役になってしまいます。
この時、断るのが苦手な人ほど、どんどん仕事を押し付けられます。
仕事の効率が良すぎる
仕事が早くスムーズに進められる人ほど、「自分がやったほうが早い」と思いますよね。
その結果、他人の仕事まで引き受けることが増え、気づいたらフォローばかりになってしまいます。
自分のキャパを超えても頑張ってしまう
「まだ大丈夫」と無理をしているうちに、気づけば仕事が山積みに..。
頼まれると断れず、限界を超えてもフォローを続けてしまうため、最終的に自分が疲れ果ててしまいます。
仕事できない人のフォローが疲れる理由4選
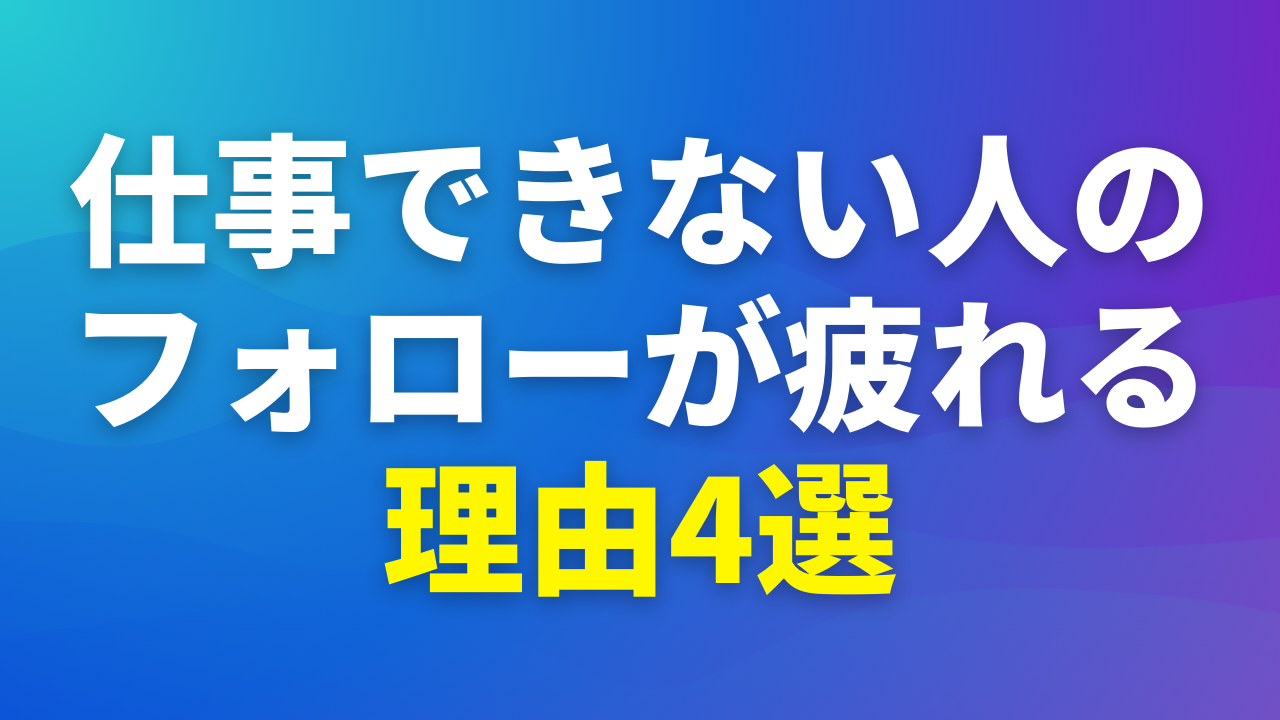
仕事ができない人をフォローは一時的ならまだしも、長期間続くと大きな負担になります。
「なぜ自分ばかり…」とストレスを感じることも多いでしょう。
ここでは、フォローが疲れると感じる主な理由を解説します。
- 仕事の負担が増える
- 精神的ストレスが大きい
- 「日々のフォロー」は評価されにくい
- 成長機会が減る
仕事の負担が増える
フォローをすればするほど、自分の業務量が増えてしまいます。
相手のミスをカバーしたり、仕事のやり方を教えたりしているうちに、自分の本来の仕事に手が回らなくなりますよね。
結果として、残業が増えたり、自分の業務のクオリティが下がったりする原因になります。
精神的ストレスが大きい
何度教えても同じミスを繰り返されたり、フォローするのが当たり前になると、イライラしてストレスが溜まります。
また、「なんで自分だけ?」という不公平感や、「助けないと仕事が進まない」というプレッシャーも精神的なストレスにつながります。
「日々のフォロー」は評価されにくい
フォローすることでチームの業務が円滑に回っていたとしても、その努力は評価されにくいものです。
上司から見ても、フォローしていること自体が目に見えにくく、「いつも問題なく進んでいる」と思われがち。
頑張っているのに感謝されず、むしろ「なんでもできる人」として、さらに仕事を任されることもあります。
成長機会が減る
フォローばかりしていると、自分のスキルアップに時間を割けなくなります。
特に、仕事ができない人のフォローに時間を取られると、自分の成長につながる業務に集中できず、新しいスキルを習得する機会を失ってしまいます。
仕事できない人のフォローで疲れた際の対処法4選
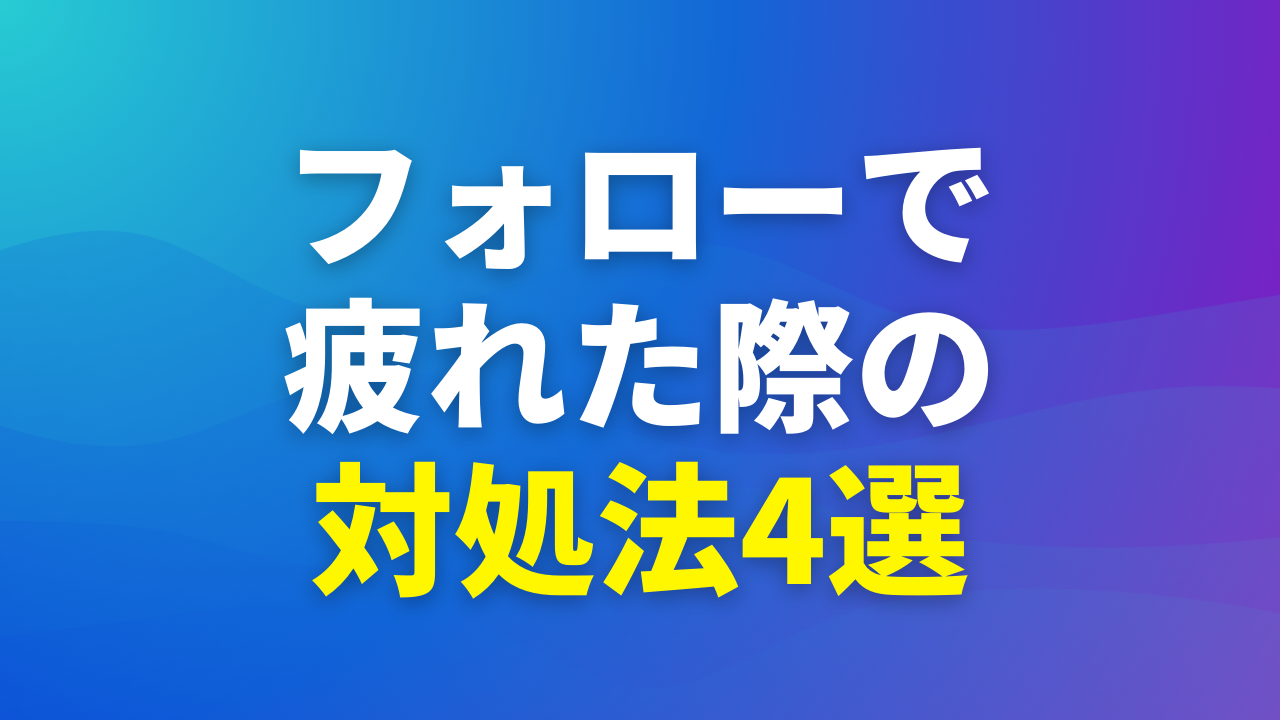
仕事ができない人のフォローをしているとストレスが溜まりますよね。
ストレスが溜まると自分の仕事にも悪影響を及ぼすので、適切な対処法を取ることが重要です。
また、それぞれの対処法に対するスキルでオススメの書籍や記事も置いておきますので、気になる方はチェックしてください。
- 仕事の線引きを明確にする
- 上司やチームに現状を共有する
- 割り切る・期待しすぎない
- 相手にスキルアップを促す
仕事の線引きを明確にする
どこまでフォローするのか、自分の役割を明確にしましょう。
必要以上に手を貸しすぎると、相手は「やってもらって当たり前」となります。
「ここからは自分の仕事」「この部分は本人にやってもらう」など、適切な線引きを意識することで、無駄なフォローを減らすことができます。
上司やチームに現状を共有する
一人で抱え込まず、上司やチームに現状を伝えましょう。
「〇〇さんのフォローで自分の業務が圧迫されている」「他のメンバーの負担も考えたい」と、冷静に現状を説明することで、業務の見直しや役割分担の調整ができるかもしれません。
特に、上司がフォローの必要性を理解していない場合、具体的に伝えることが重要です。
期待しすぎない
「なんでできないの?」「もっと頑張ってほしい」と思うほど、ストレスがたまります。
しかし、仕事ができない人に対して期待しすぎても、すぐに変わるわけではありません。
新人や後輩は十人十色で、仕事に期待せず「成長に期待」するものです。

相手にスキルアップを促す
フォローするだけでは、相手の成長にはつながりません。
できる限り「自分でやってもらう」ように促すことが大切です。
例えば、「なぜできなかった考えて見て」「ミスをした原因と対策を考えて見て」と伝え、相手が主体的に取り組むようにサポートしましょう。
教えすぎるのではなく、「任せる姿勢」 を持つことがポイントです。
こんな仕事できない社員には気を付けよう

職場には、単に仕事が遅い・ミスが多いといったレベルを超えて、周囲に大きな負担をかける「仕事できない人」も存在します。
こうした人を無理にフォローし続けると、こちらのストレスが増すばかりか、職場の雰囲気や業務効率にも悪影響を及ぼします。
ここでは、特に気をつけたい「仕事できない社員」の特徴を紹介します。
- 周囲との協調性がない
- 業務上の指示に従わない
- 逆ハラスメント
- 時間を奪っている感覚がない
周囲との協調性がない
チームワークを大切にしない人は、周りのフォローを当然のように受け入れ、自分の成長につなげようとしません。
例えば、報連相ができなかったり、助けてもらっても感謝の言葉がなかったりするタイプです。
こうした人と仕事をすると、チームの雰囲気が悪くなり、周囲の負担が増えてしまいます。
業務上の指示に従わない
「タスクが漏れないようにTodoリストを活用して」や「次の業務はこうしてください」と具体的に指示を出しても、それを守らないタイプです。
このようなタイプは、自己流で失敗します。
結果として、何度も同じことを教えることになり、周囲の時間を無駄にするだけでなく、業務の進行を妨げる要因となります。
逆ハラスメント
逆ハラスメントとは、部下から上司に対しての嫌がらせ行為です。
部下だから上司に嫌がらせをしても良いという理由にはならないので、逆ハラスメントはダメですよね。
この逆ハラスメントを注意すると、部下がさらに感情的になり暴言を吐いたり、嫌がらせ行為をする可能性もあります。
チームの雰囲気を壊す原因なので、部下への処分を検討する必要があります。
時間を貰っている感覚がない
「調べれば出てくる内容」をすぐ聞いたり、「受け身の姿勢」のままで指示待ち人間になる方は、相手の時間を貰っている感覚がありません。
新人であれば、トレーナーの時間を奪うのが仕事でもありますが、何ヶ月経っても「対応してもらうのが当たり前」の感覚の人は、非常に危険です。
こうしたタイプをフォローし続けると、自分の時間も無くなりストレスの原因になります。
仕事できない人へのダメな対応|上司・先輩は必見

仕事ができない人に対して、どのように接するかは職場の雰囲気や業務効率に大きく影響します。
フォローする側が適切な対応をしないと、自分の負担が増えるだけでなく、相手の成長も妨げてしまいます。
ここでは、特に避けるべき「ダメな対応」を紹介します。
- すべて自分でやってしまう
- 感情的に怒る
- 諦めて完全放置
すべて自分でやってしまう
「自分でやった方が早い」と思い、相手の仕事まで引き受けてしまうのはNGです。
一時的には業務がスムーズに進むかもしれませんが、相手の成長の機会を奪う且つ、何の対策にもなりません。
「どこまで任せるか」を明確にし、必要なサポートだけをする意識を心がけましょう。
感情的に怒る
ミスが続いたり、何度言っても改善されなかったりすると、ついイライラしてしまうこともあるでしょう。
しかし、感情的に怒っても相手は委縮するだけで、根本的な解決にはなりません。
また、相手が逆ギレしたり、逆ハラスメントに発展する可能性もあります。
冷静に問題点を伝え、「どう改善すべきか」を具体的に示すことが重要です。
諦めて完全放置
「この人はどうせできないから」と関与をやめてしまうと、状況はさらに悪化します。
仕事ができない人は、自分一人では改善方法がわからず、さらにミスを繰り返してしまうことが多いです。
また、周囲のサポートなしに放置された結果、他のメンバーの負担が増えたり、職場の士気が下がったりすることも..。
関わりすぎるのも問題ですが、最低限の指導やフォローは行い、職場全体のバランスを取ることが大切です。
まとめ

仕事ができない人のフォローには、思った以上に大きな負担がかかることがあります。
しかし、適切な対応を心がけることで、無駄なストレスを減らし、相手の成長を促すことが可能です。
線引きを明確にし、感情的にならず冷静に対応することが重要です。
自分のキャパシティを超えて無理をせず、必要なサポートをしながら、相手に成長の機会を与えることが、最終的にはお互いにとって最良の結果といえるでしょう。
私の転職に対する考えが変わった1冊の本を置いておきます。
オリエンタルラジオ中田敦彦さんも絶賛した、LinkedIn日本トップの村上さんの「転職2.0」になります。
ぜひ興味がある方は読んでみてください。